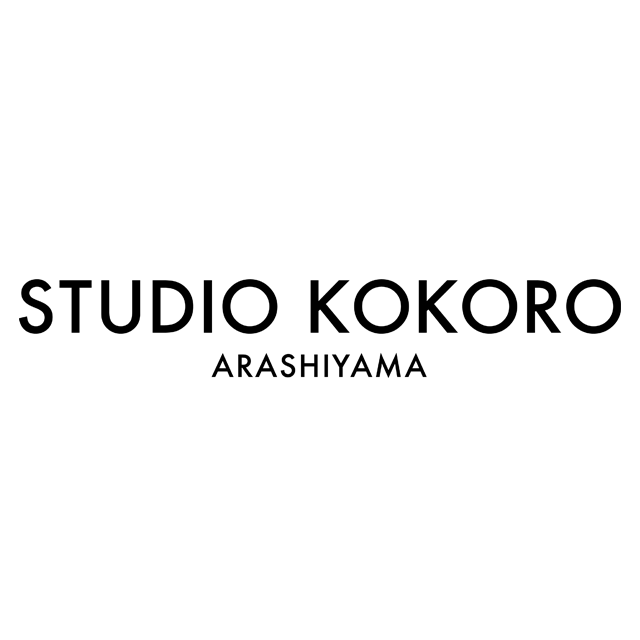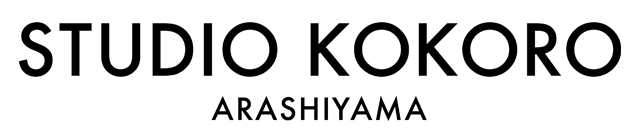舞妓さんのお着物は季節によって着るものが違います。
確かに一年中同じ種類だと暑かったり寒かったりしますよね。

~お着物と帯について~
お着物は年数で変わります!
舞妓さんのお着物や持ち物は年数を経るごとに少しずつ変わっていきます。
最初の2年程は、衿は赤に金糸銀糸の刺繍が施された華やかなもので、おこぼの鼻緒も赤で可愛らしいものです。
それ以降は、衿は白になり、おこぼの鼻緒も黄色や青など落ち着いた色にしていきます。
そうして徐々に大人の女性に近づいていくのです。
お着物だけでもここまで種類があるなんて、驚きですよね!
舞妓さんの格好にはよほど詳しい方でないとパッと見では分からない伝統や文化、こだわりが沢山あります。
お着物について少しお勉強をしてから京都に来ると、花街を歩くのがもっと楽しくなるかもしれませんね。
舞妓さんのお着物でなく、普通のお着物にもたくさんの柄があります。
そちらも併せてお勉強してみると、奥が深くてとても面白いのでお勧めです!

・お着物
舞妓さんのお着物は季節によって着るものが違います。確かに一年中同じ種類だと暑かったり寒かったりしますもんね。
季節によって種類を変えているそうです。
黒紋付はお店だしの初日から3日とお正月に着ます。
春や秋など、比較的過ごしやすい気温の時は単衣のお着物。
4月や11月といった少し肌寒く感じる季節は一枚袷のお着物。
12月~3月の真冬は二枚袷のお着物。
7月、8月の真夏は絽のお着物。
8月の”八朔(はっさく)”といわれる行事では、黒紋付(絽)を着ることがあります。
八朔とは、現在の8月1日のことで、特に京都の花街では、芸妓や舞妓がお世話になった人々に挨拶回りをする行事として知られています。
日頃の感謝を伝え、今後の変わらぬお付き合いをお願いする意味があります。
色紋付はお店だしの4日目からの時と、お正月の黒紋付を着ていないときに着ます。
お座敷の時に着るお着物も、季節によって柄が違うそうです。
例えば、春は桜、夏は風鈴や柳、秋なら菊、冬は梅や椿等、季節のお花の柄が多いそうです。

・帯
舞妓さんといえば長いだらり帯。
舞妓さんの帯は通常の帯よりも幅が広く、丈は7m近くもあります。
だらりと垂らして結ぶところからだらり帯の名前が付いたそうです。
帯自体は、一般の方が正装時に結ばれる丸帯で、金糸銀糸をたくさん使った贅沢なものです。
だらりと垂れる部分に置屋の紋が織り込まれています。
この帯を締めるのがまた大変で、着付けの先生がかなりきつく締めるそうです。
始めの頃はやはり苦しいそうですが、慣れてくると緩いほうが気になるそうです。
帯揚げや、帯締めも季節に合ったものを選びます。帯には豪華なぽっちり(帯留)を付けます。
ぽっちりはその置屋で代々受け継がれていくもので、一般の帯留と比べると、とても大きいものです。
べっ甲や銀ばどで出来た物が多く、珊瑚や真珠、宝石などが付いています。
値段が付けられないほど価値があるものなので、触らないようにしましょう。
ぽっちりや帯締めは黒紋付の時は付けないそうです。