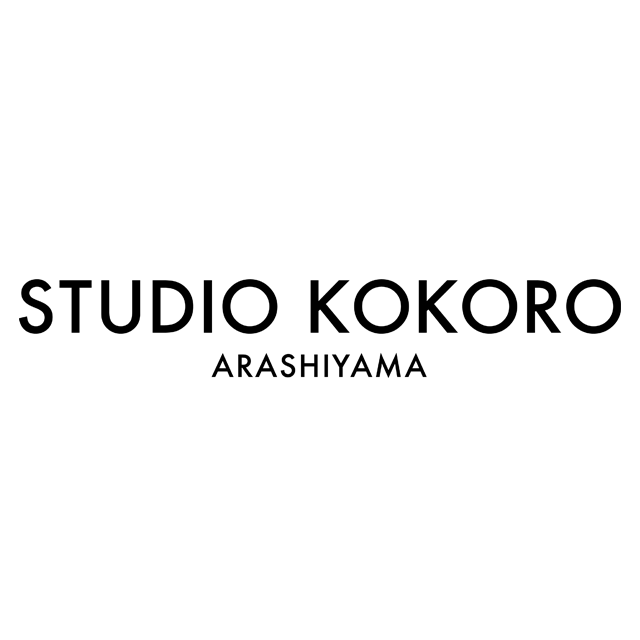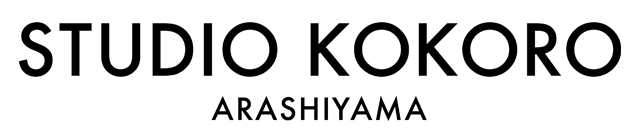舞妓体験って何?
京都文化の継承を今に残す、舞妓さん。舞妓体験では、白粉を塗り、舞妓さんの髪型をし、お引きずりの着物にだらり帯と呼ばれる背中に垂れる美しい帯を巻き、実際の舞妓さんと 同じ格好をする事で、まるで舞妓さんになったような気持ちをお楽しみいただく事が出来る体験です。 和化粧をし、舞妓さんの特別なお着物に袖を通すことで、普段なかなか味わう事の出来ない日本古来の「美」に対する価値観を体感していただいております。
舞妓体験のメイクについて
お顔全体だけでなく、首元や背中の辺りまで、白粉(おしろい)を塗っていく場所全体に対し、鬢付け(びんづけ)油を均等に塗りこみます。白粉とは、その名前の通りの真っ白な粉ですが、実は白粉にも2種類あります。先に塗っていくのは、練白粉(ねりおしろい)という固い練り物状態の物を、水に溶いて使用します。板刷毛(いたばけ)という刷毛を使って、顔全体や、デコルテの辺りまで均等に伸ばしながら塗っていきます。ここまでのお仕上がりでは、お顔はまだ真っ白なままの状態。
でも、鬢付け油や白粉が均等に塗れていないと、お顔じゅうがムラだらけになってしまい、美しい舞妓さんに変身して頂く事は出来なくなってしまう為、舞妓体験において、とても重要な工程となります。
首の後ろには、まるでアルファベットのWのような形が描かれているのはご存知でしょうか。
普段描かれるものが二本足と呼ばれるもので、お正月や八朔など、正装をする日には更に切り込みが1つ増えた三本足と呼ばれる形を塗ります。二本足や三本足などの、この化粧が施される理由は、首をより長く美しく強調する役割があるそうです。
肌を露出する事の無い舞妓さんのお着物文化にとって、唯一見える素肌である首筋の美しさは、人の目を集める魅力があるといえます。
舞妓さんの和化粧で印象的なものとして、目尻に引かれた赤いラインがあります。現代のメイクのアイシャドウとは全く異なる独特な形に描かれているそれは「厄除け」と呼ばれています。ろうそくの灯りしかなかった頃に、より美しく見せる為に塗られた白粉ですが、もちろん白粉だけを塗った状態では、生気が感じられないものになってしまいます。その為、血の色を意味する厄除けを塗ることで、白粉を塗った顔に厄が寄ってきてしまう事の無いようにするという意味合いがあるそうです。
舞妓体験としての目線として考えると、厄除けは、その形によってお顔の印象を変える大事な要素になります。キリッとした印象になったり可愛い雰囲気に仕上がったり…ただ、舞妓さんの和化粧に関しては、つけまつ毛を付ける事がありませんので、目を大きく見せる大きな役割として、アイラインの存在も大きいです。
アイラインの幅を調整する事で、左右の瞳の大きさが異なる場合のバランスを整えたり、普段のメイクのようにパッチリした瞳に見せる為に、太めに描いたりしています。 舞妓さんのメイクを施す上で、お顔の印象を大きく変化させるものとしてはもう2つあります。眉と紅です。眉は、太めの笹眉にすると、幼く可愛らしい印象、そこに少しアーチを加えて、眉尻をシャープにすると、少し洋風メイクに近い印象になり、あまり違和感を感じてしまうことなく、舞妓体験をお楽しみ頂きやすくなるのではないかと思います。さらに、シャープめに仕上げる事で、お姉さん風な仕上がりになりますので、大人っぽく仕上げてほしい人にオススメのメイクです。印象を変化させるもう1つの要素は、舞妓さんの紅。紅は、水溶きの物を使用します。実際の舞妓さんの場合は、棒紅と呼ばれるスティックタイプの紅を水に溶かして紅筆に付けて塗っていきます。普段のメイクとの違いは、真ん中にぽってりとしたカーブで塗ることで、舞妓さんならではの丸みを帯びた優しい印象に仕上がります。
舞妓体験のお着付けについて
舞妓体験の楽しみといえば、好きなお着物を選ぶ事も大きなポイントではないでしょうか。 普段の自分に似合うお着物を選びたくなるところですが、ここは変身体験。これから自分が別人に変身する事をふまえて、単純に着てみたいお着物のお色や柄で選んでしまう事をオススメします。
実際の舞妓さんですと、その季節にあった柄の着物を着て過ごします。確かに、紅葉や桜の時期にご来店なさる場合は、その季節に合わせたお着物を着たくなるもの。
でも毎月体験なさるわけではないのだから、そのご体験時に着てみたいと思ったお着物を着られると良いのではないかと考えております。STUDIO心で取り揃えている舞妓さんのお着物は、全て、正絹・総柄のお着物です。
美しいお着物に袖を通しす事で、きっと、本物の舞妓さんの気分を味わっていただく事が出来ると思います。そして、帯は「だらり帯」と呼ばれる、文字通り、背中からだらりと垂れた帯を巻きます。一般的に舞妓体験のお店では、作り帯を使用する事が多いですが、当店では、7mある帯をおお客様お一人お一人の身長に合わせて巻いて仕上げていきます。舞妓さんのお着物を選ばれる際には、同時に帯の色も合わせてお考えになると良いと思います。
STUDIO心では、メイクをさせて頂き、かつらをかぶり、その後にお着物と帯をお選びいただいております。それは、メイクを施し、舞妓さんのお顔に変身された上で、どの着物を着たいかお考え頂きたいという理由です。
実際に、お店にご来店頂くお客様でも、ご来店時は「ピンクの着物を着て可愛い舞妓さんに変身したい!」とおっしゃっている場合でも、実際にお選びになるのは紫や黒のお着物で、落ち着いたお姉さん舞妓さんに仕上がる事も少なくありません。
白粉の和化粧を施すと、幼くなる方もいらっしゃれば、反対に大人っぽく変身されるお客様もおられます。
ご体験前にある程度は「こんな着物が良いかなぁ」と想像を膨らませつつ、メイク後に改めて、着たいと思うお着物を考えてみて頂ければよいんじゃないかと思います。
舞妓体験のかつらについて
舞妓体験のお写真の仕上がりを左右する大きなポイントとして、もう一つ、かつらも重要だと考えています。
かつらには、半かつらと、全かつらという2種類があります。全かつらは、すっぽり頭にかぶるタイプのかつらです。
メリットとしては、髪の長さに左右されません。ですので、短い髪のお客様にも対応させていただく事が出来ます。
ただし、全かつらは生え際部分に網目がある為、どうしてもかつらをかぶっているということが分かってしまいます。
それに対し、半かつらの場合は、七分かつらとも言われるもので、かつらをかぶった上から前髪などの生え際の髪の毛をかぶせて仕上げます。その為、正面から見る分にはかつらだと分からなくなるほど自然な仕上がりになります。
一般的には半かつらは追加オプションとして扱われている事が多いですが、STUDIO心のこだわりとして、半かつらを無料でご利用頂いております。それは、可能な限り追加料金を頂かずにご来店頂く多くのお客様に美しい舞妓さん姿に変身して頂く事を目的としているからです。
舞妓さんの年中行事
上七軒の舞妓さんが見られる年間行事
上七軒とは・・・ 北野天満宮付近にある、京都五花街で一番古い花街。 現在30名ほどの芸舞妓さんが在籍されています。
上七軒の紋章は、五つ団子 これは豊臣秀吉が、北野天満宮で名産の御手洗団子を気に入られたことが由来と言われているそうです。
1月9日 始業式 他の花街は7日ですが、上七軒だけは唯一9日に行われます。 まずは、上七軒芸妓組合にご挨拶。 お茶屋組合に集合し、それから上七軒歌舞練場にで、新年のごあいさつや他の花街と同様、前年の売上の良いお茶屋さんや、芸舞妓さんの表彰式も行われます。 その後、始業式では舞や囃子の芸事が披露されるそうです。 ご挨拶は、「おめでとうさんどすー」「今年もよろしゅうおたの申しますー」 15日までは、稲穂のように頭をたれて謙虚に生きますという、期間限定の稲穂の簪も付けられています。
2月2日、3日 北野天満宮 節分祭 奉納舞踊 芸舞妓さんが、日本舞踊を奉納、また豆まきも行われます。 向こう一年の災厄祓いといわれています。
2月1日、2日、3日 節分おばけ これも厄払いの行事です。 仮装をして鬼や魔物を驚かし、また仮装で笑いを誘い、福を招くとも言われており、芸舞妓さんはもちろん仮装し、お茶屋さんを巡られます。 歌舞伎の連獅子、櫓のお七、外郎売、忠信、マイケルジャクソン、お姫様風、などなど、出会えればびっくりしてしまいそうな、いで立ちです。
2月25日 北野天満宮:梅花祭 約1500本という圧巻の天神さんの梅、こちらの梅苑にて芸舞妓さんによる野点が楽しめます。 芸妓さんがお点前、舞妓さんがお運びを担当されます。
3月25日~4月7日 北野をどり 上七軒歌舞練場にて、上七軒最大のイベントで、この上七軒は花柳流とされています。 一部は舞踊劇で、舞踊の要素にセリフをつけ、ストーリーに富んだ舞台。 二部は純舞踊といわれ、可愛らしい舞妓さん、艶やかな芸妓さん、さらに確かな芸をお持ちのお姐さん方の情緒あふれる舞台。 フィナーレは、上七軒夜曲で、色とりどりの華やかな舞妓さんさんと、お揃いの黒裾引姿の芸妓さんが圧巻。
6月下旬 五花街合同公演『都の賑い』 初年度は1994年。平安遷都1200年を記念して開催されるようになりました。 五花街それぞれの流派による舞踊と、舞妓さんの合同演目も見られます。 またこの期間、老舗料亭5店舗では、芸舞妓さんの舞や歓談が楽しめる、五花街の夕べも開催されます。
7月1日~9月5日 ビアガーデン 上七軒歌舞練場にて こちらのビアガーデンでは、人数によりお任せになりますが、歌舞練場のお庭、室内、欄干など、様々な席があり、趣向がこらされています。 宮川町のビアガーデンは入れ替え制ですが、上七軒はメニューもとても豊富で、入れ替えもないので、たっぷり楽しめます。 芸舞妓さんが浴衣姿でお席を回ってくださるので、その際には縁起物である、千社札をもらいたいですね。
8月1日 八朔 八月の朔日(ついたち)を省略した表現 日頃お世話になっているお茶屋さんやお店に挨拶周りに行かれます。 もちろんお姉さんにも「おめでとうさんどすー」と挨拶して回られます。 ※もとは農民が恩人に初穂を贈ったことから、『田の実の節句』と言われたそう。 その農家の風習が武家や公家、そして一般にも広まり、「田の実」が「頼み」に代わり、日ごろ頼み事をしている人に挨拶に行くという風習にかわったといわれています。 現在も続いているのは、花街くらいといわれているそうです。
10月1日~4日 北野天満宮ずいき祭 天神さん最大のお祭りで、4日の還幸祭では、お茶屋さんの玄関前で芸舞妓さんも並んで見送られています。
10月8日~12日 寿会 もともと上七軒は寿仲間という組合ではじまったとされ、おさらいをする会の温習会の名称に寿の文字をとり、寿会と命名されたそう。 上七軒歌舞練場で公演され、古典が中心の演目を観覧できます。
10月22日 時代祭 毎年、五花街の芸舞妓が交代で参加されます。
11月23日 祇園小唄祭 祇園小唄とは、舞妓さんが修行期間の仕込みさんの頃から習い、毎日のように舞う舞踊曲。 円山公園に建立された歌碑の前で舞妓さんが歌詞を朗読し、献花が行われます。
12月初旬 南座顔見世総見 南座の顔見世興行を、各花街ごとに芸舞妓さんが揃って観劇し、舞や三味線の芸事の勉強をする恒例行事。 この日の舞妓さんの花かんざしは『まねき』で、そこに好きな役者にサインをもらう習わしがあります。 南座が耐震工事中の、2016年は先斗町歌舞練場、2017年はロームシアターで開催されました。
12月1日 献茶祭 北野天満宮で行われる大茶会。 京都の4家元2宗匠が6年ごとに奉仕、境内に茶席が設けられます。 この日も芸舞妓さんによる野点があります。
12月13日 事始め お正月の準備を始める日で、お世話になっているお茶屋さんやお師匠さんのところ、また普段お世話になっているお店に挨拶にいき、鏡餅を納める。 「おことうさんどすー」とご挨拶し、1年の感謝を伝え、来年の精進を誓う日。
12月31日 おことうさん・おけら火 この行事は祇園で主に行われてきたもの。 お世話になっているお茶屋さんを巡ってご挨拶し、お茶屋さんからお年玉の代わりに紅白の福玉をいただく。 外は餅皮やもなかの皮でできており、中に縁起物が入っている。 除夜の鐘が鳴り終わってからあけるのが習わしで、中の小さい縁起物により、それぞれ意味があり新年を占うとも言われている。 現在は京都出身の芸舞妓さんが減り、郷里に帰る舞妓が増え、見ることが少なくなってきているといわれている。